最終更新日2024.6.03(公開日:2024.6.03)
監修者:営業責任者 渥美
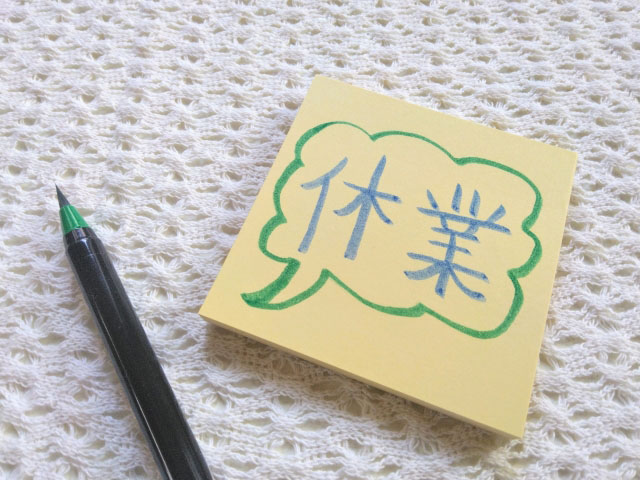
休業補償給付は、労働者が業務上の事由により怪我や病気を負った場合に、休業期間中の生活を保障するために支給される労災保険の給付の一つです。
休業補償給付を受けるためには、所定の手続きを経て労働基準監督署に申請する必要があります。
通勤災害の場合は少し内容が異なり、休業給付と呼びます。
休業補償給付(休業給付)を受けるための主な要件は以下の通りです。
業務上の事由とは、仕事が原因で怪我や病気を負ったことを指します。決していいケースではありませんが、電車通勤であるはずの者が会社に黙って、自転車通勤していた際の事故なども労災休業給付の対象になることが多いです。
しかし、休日に会社に忘れ物を取りに行く途中でケガをした場合などは、休日出勤して働くわけでなければ仕事とは関係ありませんので、労災とは認められません。私的な理由による怪我や病気は、休業補償給付の対象外です。
怪我や病気の療養のために仕事を休み、その期間中に賃金を受けられない状態であることが必要です。
休業中に賃金の一部または全部が支払われている場合は、その分だけ休業補償給付が減額されます。
休業補償給付は、休業期間が4日以上である場合に支給されます。休業期間が4日未満の場合は、休業補償給付の対象外となります。休業1日目から3日目のことを待機期間と呼び、給付は4日目から支給されます。
休業4日未満の業務上災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。対して、通勤災害の場合は使用者が休業補償を行う必要はありません。
休業補償給付の申請手続きは、以下の流れで行います。
無論、業務上の事由により怪我や病気を負った場合、悠長に病院を選ぶわけにはいきません。
指定外病院だと全額払って、その分の医療費を労基署に請求することになります。労災指定病院の場合は医療費が無料です。
労災保険指定医療機関は、労災保険の取扱いに関する知識と経験を有する医療機関であり、ネット上で調べることが可能です。
休業補償給付を受けるには、休業補償給付支給請求書を作成する必要があります。
請求書には、労働者の氏名、住所、病名、休業期間、賃金額等を記入します。
医師が証明すべき記入事項は「傷病名や労務不能期間等を証明する医師の意見」「業務上の事由であることを証明する事業主の証明」です。請求書の様式は、労働基準監督署や厚生労働省のホームページから入手できます。
本人が事実関係を(事業主が代行する場合がほとんど)、事業主が記載する事実関係を証明、医師が労務不能であることを医学的に証明しますので、1式の請求書を3者で証明することになります。
作成した休業補償給付支給請求書を、管轄の労働基準監督署に提出します。
申請は各企業の給料締め日以降に行うのが一般的ですが、厳密な定めは特にありません。また、「療養補償給付」にも厚生労働省のホームページから引用して触れておきます。
『療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。』
休業補償給付の申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。
休業補償給付の申請期限は、休業補償の対象となる日から2年以内です。申請が遅れると休業補償給付を受けられないため、注意が必要です。
休業補償給付支給請求書の記入内容に誤りがあると、給付の支給が遅れたり、不支給となったりする可能性があります。請求書の内容を確認し、正確に記入することが重要です。
実際にあった不正受給の事例を挙げます。
N県の65歳の男性が労災に遭い、当時勤めていた会社を休業した後退職、以降は休業補償給付を受けて療養していましたが、別の会社に就職。
「業務上の疾病による療養のため働けず、賃金を受けていない」と虚偽の請求書を提出して休業補償給付金約530万円と休業特別支給金約177万円を詐取していました。
また、この男性が別件で労災保険請求を行った際に不正受給が発覚しました。管轄労基署は「医者が要休業と認めた身体状態でありながら働いていたということであり、通常起こり得ない事案」としています。
また、罰則について労働者災害補償保険法第12条の3を引用しておきます。
『偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。』
休業補償給付を不正に受給した場合必ず発見されますし、返還請求や刑事罰の対象となる可能性があります。不正受給は厳しく罰せられるため、適正な申請を心がけましょう。
休業補償給付は、怪我や病気による休業中の生活のための制度ですが、必ずしも十分な補償とは言えません。
休業補償給付の支給額は、原則として休業前の賃金の8割程度に留まるためです。つまり賃金の満額ではなく2割程度は補われないことを覚えておきましょう。
そこで、労働者の生活をより手厚く保障するために、企業が独自に上乗せ補償を行うケースがあります。
上乗せ補償の内容は企業によって異なりますが、休業補償給付と合わせて、休業前の賃金の100%を補償するケースもあります。
上乗せ補償は、労働者の安心感につながるとともに、企業の福利厚生の充実を示すものとして、重要な意味を持っています。
特に、優秀な人材の確保や定着率の向上を目指す企業にとって、上乗せ補償は有効な施策の一つと言えるかもしれません。
休業補償給付の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされます。申請の際に不安がある場合は、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。社会保険労務士は、労災保険を含む社会保険の手続きに精通した専門家です。
社会保険労務士に相談するメリットは、以下の通りです。
休業補償給付支給請求書の作成を社会保険労務士に依頼することで、手続きを代行してくれるので、書類の不備や記入ミスを防ぐことができます。
社会保険労務士から、休業補償給付の申請手続きの流れや注意点について、詳しい説明を受けられます。スムーズな申請につながります。
社会保険労務士のアドバイスを受けることで、休業補償給付が不支給や不正受給となるリスクを減らすことができます。
休業補償給付は、業務上の事由または通勤により怪我や病気を負った労働者の生活を保障するための重要な制度です。休業補償給付を受けるには、所定の手続きを経て、労働基準監督署に申請する必要があります。
申請の際は、休業補償給付支給請求書を作成し、医師の意見書等を記入します。申請期限や申請内容の正確性には、十分な注意が必要です。申請手続きに不安がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
休業補償給付の上乗せ補償を行う企業もあります。上乗せ補償は、労働者の生活をより手厚く保障するとともに、企業の福利厚生の充実を示すものとして、重要な意味を持っています。
業務上の怪我や病気は、誰にでも起こり得るものです。もしものときに備えて、休業補償給付制度についての理解を深めておくことが大切です。
弊所サービスに関するご質問やお見積もりのご依頼は
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。