労災休業補償の対象は、次の要件をすべて満たす労働者です。
- ・業務上負傷または疾病にかかったこと
- ・労災により休業したこと
- ・労災保険に加入していること
- ・休業期間が4日以上であること
- ・労災保険法の適用を受ける事業所に勤務していること
最終更新日2025.2.26(公開日:2024.4.24)
監修者:営業責任者 渥美 瞬
監修協力:社会保険労務士 河守 勝彦

労災休業補償について本記事では解説します。
労災保険は労働者を雇用すると企業には加入義務があり、労働災害による傷病や障害を補償するものです。
労働者が労災にあった際の労災休業補償の基礎知識から対象者、計算方法、申請手続き、注意点、労災隠しなどを解説します。
また、絶対に行ってはならない労災隠しについても実例、罰則なども挙げながら合わせて解説していきます。
本記事で説明する内容は以下の通りです。
労災休業補償は、労働者が業務上負傷または疾病(以下「労災」という)により休業した場合に支払われる補償制度です。収入の補填や治療費などの労災費用を労働者に支給し、労働者の経済的負担を軽減することを目的としています。
休業補償の対象となる労働災害は、業務上の事故や病気、通勤途中の事故によるもので、その結果働けなくなった労働者が対象となります。
ただし、自己責任による事故や病気、業務と無関係の私事による事故は対象外です。
労災休業補償の受給には申請手続きが必要です。具体的な手続きは、労働者が事業主に届け出ることを始め、医師の診断書や事故の詳細などが必要になります。
労災休業補償の対象は、次の要件をすべて満たす労働者です。

対象となる労働者は、事業主との雇用契約がある者で、業務上の傷病や事故により医師によって休業が必要と判断され、療養や休業が必要となる者です。
ただし、一部の労働者(例:家政婦や個人事業主の助手)は対象外です。
また、通勤途中の事故による傷病も対象となりますが、事業主との雇用契約がない者や自己責任による事故は対象外となります。
労災休業補償の支給額は、どのように算出されるか厚労省のホームページから引用します。
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
※給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額のことです。
休業日数とは、労災により労働者が業務に就けなくなった期間のことです。
休業日数は、労災発生日から医師の診断により就労不能とされた日から、医師の診断により就労可能とされた日までのことを言います。
労災休業補償は、休業期間が3年を超える場合を除き、休業期間中支給されます。ただし、以下のような場合は支給期間が制限されます。
労働者の治療が継続し、労働に復帰できない場合、休業補償の支給期間が延長されることがあります。治療期間が長引く場合には、その他の制度(障害年金等)の利用も検討する必要があります。
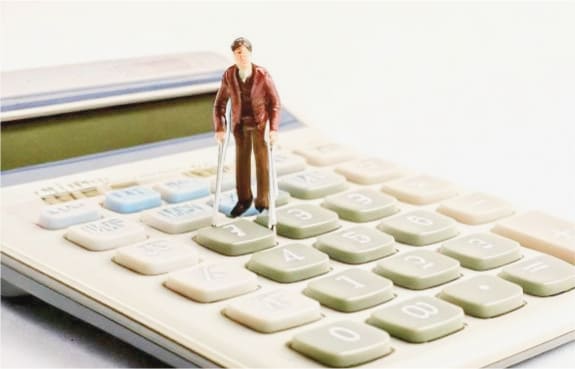
労災休業補償を申請するには、労働者は以下の手順に従う必要があります。
労災休業補償の申請に必要な書類は、労働者が補償を受けるために重要です。
主な書類としては、事故報告書、受診日数の証明、治療費の領収書、医師の証明書があります。
医師の証明書は必要不可欠であり、この証明書には、労働者の傷病・障害の原因や程度、治療内容、期間などが記載されます。
また、治療費用の請求には、医療機関からの領収書や治療費明細が必要です。これらの書類は、労働基準監督署に提出し、審査されたのちに補償が決定されます。
無論、業務上の事由により怪我や病気を負った場合、悠長に病院を選ぶわけにはいきません。 指定外病院だと全額払って、その分の医療費を労基署に請求することになります。労災指定病院の場合は医療費が無料です。
労災保険指定医療機関は、労災保険の取扱いに関する知識と経験を有する医療機関であり、ネット上で調べることが可能です。
休業補償給付は、怪我や病気による休業中の生活のための制度ですが、必ずしも十分な補償とは言えません。
休業補償給付の支給額は、原則として休業前の賃金の8割程度に留まるためです。つまり賃金の満額ではなく2割程度は補われないことを覚えておきましょう。
そこで、労働者の生活をより手厚く保障するために、企業が独自に上乗せ補償を行うケースがあります。
上乗せ補償の内容は企業によって異なりますが、休業補償給付と合わせて、休業前の賃金の100%を補償するケースもあります。
上乗せ補償は、労働者の安心感につながるとともに、企業の福利厚生の充実を示すものとして、重要な意味を持っています。
特に、優秀な人材の確保や定着率の向上を目指す企業にとって、上乗せ補償は有効な施策の一つと言えるかもしれません。
休業補償給付の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされます。申請の際に不安がある場合は、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。社会保険労務士は、労災保険を含む社会保険の手続きに精通した専門家です。
社会保険労務士に相談するメリットは、以下の通りです。
休業補償給付支給請求書の作成を社会保険労務士に依頼することで、手続きを代行してくれるので、書類の不備や記入ミスを防ぐことができます。
社会保険労務士から、休業補償給付の申請手続きの流れや注意点について、詳しい説明を受けられます。スムーズな申請につながります。
社会保険労務士のアドバイスを受けることで、休業補償給付が不支給や不正受給となるリスクを減らすことができます。
労災隠しとは、企業が労働者の労災事故を報告せず、手続きや補償を行わない行為です。企業が労災隠しを行う理由としては、労災が発生すると、企業の評判が傷つく可能性があり、労働者の管理体制について責任を問われます。
労災の発生原因や企業の安全管理体制を明らかにすることを目的として、労働基準監督署からの調査も入り、厳しく調査されます。
以下、労働基準監督署による調査の内容を挙げます。
管理体制の不備が見つかると「是正勧告」を受けますし、最悪の場合は営業停止になる可能性もあります。
そのため労災隠しという、重大な違反を企業が行うことがあります。
労働者側としての労災隠しについての相談窓口は、各地域労働局や労働基準監督署があります。また、労働法に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
ケースとして多くある労災隠しの実例を挙げます、厚生労働省のホームページから以下引用します。
『労働災害が発覚するまで「労働者死傷病報告」を提出しなかったとして○○労働基準監督署は労働安全衛生法違反の疑いで、2次下請である塗装業Bの代表○○と3次下請の塗装業Cの代表○○を○○地方検察庁に書類送検した。
マンション新築現場で、Cの作業員が吹き付け塗装をするためのシート張りをする際、転倒し右手首を複雑骨折したが、BとCは共謀して、「受注を確保するために元請けに労災保険で迷惑をかけたくない。」として労働災害を隠蔽したもの。』
労災隠ぺいは、労働者の健康や安全を脅かし、企業の社会的責任を損なう重大な違反行為です。罰則の適用は、労災隠ぺいの程度や結果によって異なります。
以下に例を挙げます。
休業補償給付は、労働者が業務上負傷または疾病により休業した場合に支払われる補償制度です。休業補償給付を受けるには、所定の手続きを経て、労働基準監督署に申請する必要があります。
申請の際は、休業補償給付支給請求書を作成し、医師の意見書等を記入します。申請期限や申請内容の正確性には、十分な注意が必要です。申請手続きに不安がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
企業側としては決して労災隠しを行ってはなりません。重大な違反となり、懲役刑を含む重い罰則が科せられる可能性があります。労災が発生した場合は、速やかに適切な対応を取ることが重要です。
休業補償給付の上乗せ補償を行う企業もあります。上乗せ補償は、労働者の生活をより手厚く保障するとともに、企業の福利厚生の充実を示すものとして、重要な意味を持っています。
業務上の怪我や病気は、誰にでも起こり得るものです。もしものときに備えて、休業補償給付制度についての理解を深めておくことが大切です。
弊所サービスに関するご質問やお見積もりのご依頼は
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。